本稿の目的は、著者の学生時代における起業経験を基に、産学の隔たりとその要因を明らかにし、それらを体系化する事である。本稿における産学の定義は、産業界と文科系の大学、及び文科系の学部に通う学生である。
著者は学生時代に大学のゼミナールの友人達(甲斐太平衛、山本憲明)と共に第1回学生起業家選手権大会[1]に出場し、最高賞に値する優秀賞を受賞。その副賞として東京都から助成された300万円を資本金として有限会社ピー・アイ・ピー[2]を設立した起業経験を持つ。
社会通念からすると、学生が会社を経営することそれ自体が無謀にも思われるが、産業界からは学生という立場での企業経営者が特異な存在に映るため、必然と多くの企業やメディアから注目を浴びることになり、学生であることで有利にビジネスを展開できたこともしばしばあった。一方でそうしたチャンスを経験の無さから活かせず功罪相償うこともあり、ビジネスの現場においては一概に学生であることが有利であるとも不利であるとも言えない、というのが著者の見解である。具体的には、学生起業家というもの珍しさで興味を持ってもらえる企業が多数あったが、経験と人脈の欠如からその多様な要望に応えきれなかったり、多くのメディアに取り上げられた反面、湾曲したメッセージがマスに対して伝えられたりと、学生であるからこそ得ることが出来たチャンスもあれば、社会経験のほとんどない学生であることが大きな弊害となったこともしばしばあった。
本稿ではそうした著者の体験と所感から、学生ベンチャーに対する実社会の反応と行動パターンの一端を示すことを試みる。第1章で著者の起業までの経緯を解説し、起業の目的や経緯を述べた上でそれらの時系列を示す。第2章では学生ベンチャーとして起業した企業に対する各方面の反応と学生の感覚と比較し、第3章で産学の隔たりの要因を明らかにし総括する。
起業に対して、学生はもちろん産業界でさえもまだ、「学生は実社会と縁遠い存在」という意識や「学生がビジネスを展開することは難しい」という先入観が蔓延っているようである。本稿が学生ベンチャー企業の創出、ならびに産業界の学生ベンチャー企業に対する既成概念の払拭に貢献できれば幸いである。
なお本稿はその性質上、文献による調査は行わず、体験と所感を基にした定性的観点からの考察を基に論じている。前以てご理解いただきたい。
1−1 学生起業家選手権出場までの経緯
著者が起業するきっかけとなった「学生起業家選手権」への出場は、自らの強い起業への思いからではなく、ゼミナールの活動の一環として、半ばプランニングやプレゼンテーションのトレーニングを目的として果たしたものである。ここでは著者が学生起業家選手権に出場するまでの具体的な経緯を述べたい。
著者は青山学院大学国際政治経済学部の岩井千明ゼミナールに所属し、大学3年次の学園祭でゼミナール主催のイベントとしてビジネスプランコンテスト『Chiakiの虎[3]』を企画。出場者を公募したもののプロモーション不足から殆ど応募が無く、やむを得ずゼミナールの学生が出場することとなった。このとき、必要に迫られてゼミナールの学生の発案で生まれたビジネスプランが、後に学生起業家選手権で優秀賞を受賞することになる『渋谷発!pip(ピッピ)で情報交換ブーム![4]』(以下pipプロジェクト)である。
実はこの時点ではあくまで学園祭イベントを成功させるためのアイデアが生まれただけに過ぎず、当時のメンバー[5]は誰一人として起業を意識してはいなかった。もちろん学園祭イベントでプレゼンテーションするためにプランを煮詰め、事業計画書などの資料を作成する過程では、実現させることを想定した資金計画やマーケティング戦略を考えていったわけだが、仮に実現させるとしても会社を設立すること、すなわち起業することに必要性と現実味を感じず、学生の立場でのプロジェクトを想定していた。
その後、学園祭での発表を果たしたところ審査員から高く評価され、またゼミナールの担当教諭である岩井千明先生から、より公的な場での発表を薦められたこともあり、pipプロジェクトメンバーで学生起業家選手権に出場することを決意したのである。
このように、pipプロジェクトメンバーは当初から起業を目的としてpipプロジェクトを完成させたのではなく、あくまで目の前のチャンスに確実に手を出した結果が好機を生み出したと言える。しかしそのたった一つの成果が、大学での受動的な講義とは比較にならないほどスキルとして自己に蓄積されていくのをひしひしと感じ取れたのもまた事実である。
起業してから気づいたことではあるが、大学内外に因らず“起業はある特定層だけに許された敷居の高いもの”と考える人が多数であり、学生起業家選手権への出場の経緯などを説明する度にその自然体な姿勢に驚かれたのが印象的であった。学生生活の成果の一つとして実際に起業を果たした自分達と、起業した結果だけを見た人との間には、かなり大きな感覚の隔たりがあることを強く感じたものである。
1−2 起業の決意から会社設立まで
pipプロジェクトのメンバー3名が起業を意識し始めたのは学生起業家選手権決勝大会で優秀賞を受賞し300万円が助成されることが決まった瞬間である。先に述べた通り、そもそもメンバーの3名は会社設立を目的として学生起業家選手権に出場したのではなく、あくまで「学園祭イベントの延長線」という感覚が支配的であったため、優秀賞受賞の瞬間も会社を設立することができる喜びというよりは、自分達で考えたビジネスプランが対外的に評価されたことに対する達成感と充実感が大きかった。もちろん会社を設立できるチャンスを手に入れたことはポジティブに捉え、そのチャンスを最大限に活かしたいという思いは皆共有していたが、会社設立それ自体に魅力を感じていたのではなく、自身の成長や各自が抱く思いを達成する場として、自分で勝ち取った会社を利用できることに大きな期待と目的意識を抱いていた。
さて、ここまでは順調に結果を残してきたわけだが、実際に会社を設立するとなると予想以上に多くの手順を踏まなければならない。それまで会社設立に関する予備知識といえば、大学での講義や文献から得たものばかりで、会社設立までの大きな流れは把握していたが、例えば定款[6]を作成するにしても実際に掛かる費用や時間、及び労力などを把握できるはずもなく、全てを手探りで進めていった。
ここで、会社設立の際に最も重要な手順のひとつである定款の作成について述べたい。定款の作成というと、非常に多くの時間と労力を要するもの、もしくは専門家に依頼して多額の費用がかかるもの、という印象を持つ人も多いが、実際には市販の書籍に従い、自宅のパソコンでテンプレートに当てはめていくだけで大枠は完成してしまう。(もちろんこうしたことが可能になってきたのはここ数年のことではあるが。)ただし、すべてをテンプレートに従うわけではなく、一部は自分で考えて記載しなければならない。それらのなかで、最も重要かつ難解な手順は事業内容の明文化である。もちろん何らかの事業目的を持って会社を設立するわけであるから、創設者にとってその会社の事業内容は明らかである。またそれを単純に明文化することはそれほど難解なものではない。しかしながら、その事業目的を、法務局が認可を下すような文言に置き換え、端的に示すことが一般市民には極めて難解なのである。
pipプロジェクトは広告業であるが、将来的な事業として学生のネットワークを利用したさまざまなアイデアを模索していた。そのことを、pipプロジェクトを支援していただいている会計士の方に相談したところ、「やや的外れかもしれないが定款に載せる場合はコンサルティング事業と書かなければ認可が下りないかもしれない」とアドバイスをいただいた。とりわけ文言に拘ってビジネスを始めるつもりはなかったが、定款の謄本などは法務局に申請すれば誰でも自由に取り出せるものであるから、仮にそれを見た人が実際の事業とあまりにもかけ離れた事業をイメージしてしまう可能性があることは、大きな問題だと感じざるを得ない。
一学生である自分の感覚と実社会でのルールとの違いに右往左往しながらも、メンバー3名がそれぞれ100万円ずつの出資者となり、学生起業家選手権決勝大会のちょうど3ヵ月後にあたる6月10日に有限会社ピー・アイ・ピーを設立することとなった。会社を設立してから気づいたことであるが、会社を設立し一定の手続きが終わった時には、実にメンバー3名で40万円にも上る資金を立て替えており、実際に設立開業準備費[7]の総額を見たときには、自分自身で会社を起こし動かそうとしていることを再認識した。
なお、学園祭でのイベントの立案から実際に起業するまでの経緯と時系列を1-3で一覧にした。会社設立の大きな流れをつかむ目的で参照されたい。
1−3 起業までのタイムスケジュール
2002年8月15日
2002年度青山祭(青山学院大学学園祭)でゼミナールイベント『Chiakiの虎』を主催することが決定。
2002年10月18日
ゼミナールメンバーからpipプロジェクトの原型となるアイデアが創出。学園祭でのイベントに向けてプレゼンテーション資料などの作成を開始。
2002年10月25日
ゼミナール担当教諭の岩井千明先生の勧めでpipプロジェクトをビジネスプランとして学生起業家選手権に出場することが決定。
2002年10月31日 ―学生起業家選手権一次審査書類提出期限―
学生起業家選手権へのエントリーを完了する。(全国から合計79組が応募)
2002年11月2日 ―2002年度青山祭当日―
pipプロジェクトが公的な場としては初めて発表される。審査員として招いていた政府系ベンチャーキャピタルのS氏より実現可能性の高さを評価され、プロジェクトの実現を目指すことを勧められる。しかしリスクの大きい起業は勧められないとの忠告も同時に受ける。
2002年11月11日 ―学生起業家選手権一次書類選考結果発表―
学生起業家選手権書類選考に通過。(52組が書類選考を通過)
2002年11月25日 ―学生起業家選手権予選プレゼンテーション当日―
東京都立川市の東京都中小企業振興公社にて、第1回学生起業家選手権予選公開プレゼンテーションが開催される。
2002年12月8日 ―学生起業家選手権経営試験当日―
学生起業家選手権で唯一の筆記試験が行われる。本選手権でpipプロジェクトメンバーで代表者になっていた甲斐太平衛が筆記試験を受験する。
2002年12月24日
東京都中小企業振興公社より、学生起業家選手権予選通過内定の知らせを受ける。
2003年2月4日
東京MXテレビ「東京リトルガリバー」で学生起業家選手権を取り上げるため、撮影が開始される。
2003年2月26日
株式会社ベンチャーリンク本社にてオンラインマガジン「VEN-VEN[8]」のインタビューを受ける。
2003年3月10日 ―学生起業家選手権決勝プレゼンテーション当日―
学生起業家選手権の決勝大会が東京都庁第二本庁舎1階(第二本庁舎ホール)で行われ、最高賞に値する優秀賞を受賞。副賞として東京都から300万円が助成される。その日の夜にはNHKの首都圏ニュースでその模様が放送された。
2003年3月11日
学生起業家選手権決勝大会の結果が、日本経済新聞、日経産業新聞、朝日新聞にそれぞれ掲載される。
2003年3月16日
東京MXテレビ「東京リトルガリバー」で学生起業家選手権のことが放送される。pipプロジェクトについても約15分間放送された。
2003年3月26日
株式会社山櫻[9]本社にて市瀬和敏常務(株式会社山櫻)と岸本法雄取締役(Growing Business Support 株式会社[10])と出会う。
2003年4月16日
市瀬常務の紹介で、渋谷区道玄坂の内川清雄会計士税理士事務所[11]を訪問する。会計士の内川先生や塚田先生と出会い、その後の会社設立手続きの指導を受ける。また、オフィスを持っていなかった自分達の為に、簡単な打ち合わせと本店所在地(定款に記載)としての利用に関して、事務所の利用を認めていただいた。会社設立において最も弊害であった定款の作成に目途が立ち、企業に向けて一気に加速していった。
2003年4月21日
東京法務局渋谷出張所にて類似商号調査を行う。
2003年4月24日
東京都の知的財産センターにビジネスモデル特許を取得できるかどうか確認しに行く。このとき、特許取得が出来なくなっている[12]ことを知り、商標登録など可能な保護を施してビジネスを展開することになった。
2003年5月8日
日本テレビ「きょうの出来事」の取材が開始される。
2003年5月14日
定款を法務局に提出し、有限会社ピー・アイ・ピーの設立手続きを開始する。
2003年5月19日
みずほ銀行渋谷中央支店を訪問し、法人用銀行口座の開設について相談する。
2003年5月22日
東京都庁創業支援課を訪問し、学生起業家選手権での優秀賞受賞に伴う助成金交付申請書を提出する。
2003年6月2日
特許庁を訪問し、pipロゴデザインの商標登録申請書[13]を提出する。
2003年6月9日
みずほ銀行渋谷中央支店より、出資金保管証明書が発行される。
2003年6月10日 ―有限会社ピー・アイ・ピー創立―
東京法務局渋谷出張所にて有限会社ピー・アイ・ピー設立登記完了。メンバー3名がそれぞれ会社役員に就任する。午前中に登記を完了し、午後から青山学院大学構内にてpipの配布イベントを決行した。
2003年6月18日
東京都中小企業振興公社に出資金保管証明を提出する。
2003年6月24日
東京法務局渋谷出張所にて登記簿謄本、及び代表取締役印の印鑑証明を取得。
2003年6月25日
東京都中小企業振興公社に定款謄本と登記簿謄本を提出。
2003年7月3日
渋谷区税務署に法人設立届出書等、納税に関する書類を提出する。同時に都税事務所に事業開始等申告書を提出する。
1−4 小括
会社設立に関して起こった諸問題に対してはその都度対処し、決して焦ることなく段階を踏んでいった結果、特に大きな問題も無く会社設立が完了した。社会経験の無い学生であっても、必要な知識をその場で得ていくことで大抵の問題はクリアできるのである。
一方で、著者を含むpipプロジェクトメンバーは、起業することを目的としたことは無く、また起業に対して敷居の高さや抵抗感を感じたことも無かった。学園祭でのイベントからスタートし、自然体に目の前のチャンスに手を出してきた結果として起業するに至ったわけだが、決して起業そのものを軽視しているのではなく、起業はゴールではなく広義に人生の選択肢の一つであるという考えにおいてメンバーの意識が一致していた、ということである。
つまり、起業を通じて得ようとする経験や知識、また達成したい思いは3人それぞれが異なっていたが、起業のあり方や起業がひとつの手段に過ぎないという考え方においてはメンバー間でコンセンサスを得ており、そのことがチームワークの良さにつながり、起業家選手権での好成績につながったと考えられるのである。
2−1 メディアの反応
pipプロジェクトが学生起業家選手権の決勝大会に進出することが決まってから会社設立後まで、実に多くのメディアから取材を受けた[14]。学生起業家選手権で優秀賞を取った3組のなかでもとりわけpipプロジェクトは多くのメディアに取り上げられたが、その背景には優秀賞を受賞した3組のなかで、在学中に会社設立できる見込みが高かったのがpipプロジェクトだけであった[15]ことに加え、名刺の裏面に広告を載せるという単純さがメディアに表現し易いから[16]であった。
もちろんメディアに掲載されることそれ自体は設立した会社の広報宣伝活動にもなり、一般にベンチャー企業に最も欠けているとされる「信用力」を補填する恰好の機会となった。しかしながら、実際に多くのメディアに掲載されると問題点も浮かび上がってきた。それは、湾曲したメッセージの伝達である。
メディアの影響力は使い方次第で多大なプロモーション効果を生むが、ひとつ間違えば組織に大きなダメージを及ぼしかねない諸刃の剣だと言える。例えば全国放送のテレビ番組の場合、視聴率が10%で1200万人の視聴者にリーチしてしまう。しかも、テレビ放送の場合はコンテンツの事前チェックなどは殆どなく[17]、実際に放送されたときに自分達が伝いたいメッセージとは異なるイメージや映像が流れてしまったとしても取り返しがつかないことは、あまり知られていないのが現状である。pipプロジェクトにおいて、メディアへの掲載は確かに認知度を高める宣伝効果は絶大であったが、同時に「自分達の経営資源で可能な範囲を逸脱した期待を掛けられる」ことにもなった。つまり、メディアに掲載されたことで実際の企業規模や経営資源をはるかに超えた姿として大衆にリーチしてしまい、過剰な期待を抱かせる結果となったのである。その結果、多くの企業からのアプローチを受けたがその多くがミスマッチに終わってしまったという時間的コストのロスがあったのである。
これまでpipプロジェクトがメディアに取り上げられたものの多くは学生起業家として、pipプロジェクトメンバー3名に焦点をあてたものであったために、多少の湾曲したメッセージでも企業イメージのダウンなど、会社への打撃は殆ど無く、むしろpip申込者の急増や企業からの問い合わせ数増加などのポジティブな効果が目立った。しかし、これが例えば特定の商品やサービスについての映像や記事であり、メッセージが大きく湾曲されて伝わったとするならばその影響はあまりにも大きな力となり、ベンチャー企業にとっては死活問題になりかねないことに後から気づいた。同時に、メディアへの露出を利用することで、単なる記事や紹介にとどまらず、多大なプロモーションにつなげることが出来たことを悔やんだこともあった。
pipプロジェクトにおいてはこれまで、メディアの影響が深刻な打撃となったことは無い。しかし、一方的にメディアにpipが取り上げられ続ければ、口コミを通じて学生マーケットを開拓していこうとするpipプロジェクトでは湾曲したままのメッセージがマスに浸透し、現実の姿との矛盾をユーザーに感じさせてしまう可能性があり、慎重に掲載メディアを選択し、過不足無いメッセージを伝達できるように努めなければならないと感じた。
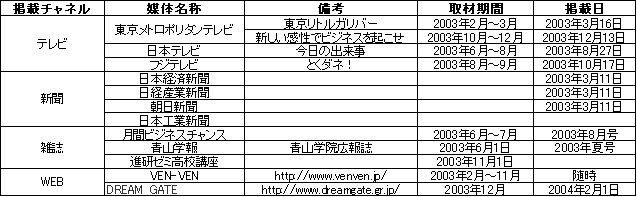
表 1:メディア掲載実績
2−2 産業界の反応
メディアに取り上げられると各種メーカーや広告代理店など、多くの企業から問い合わせが入るようになり、それらと実際に交渉をすることになった。これは先に述べたとおり、ベンチャー企業に不足しがちな信用力を、「学生起業家選手権の優秀賞受賞」と「各種メディアへの露出」で補ったことが大きく寄与している。
民間企業が有限会社ピー・アイ・ピーに対して抱く印象は様々であったが、多くの企業人と話を進めるうち、彼らが学生ベンチャーに対して抱いている共通した想いがあることに気づいた。
まず、実社会で活躍する社会人の多くは、学生ベンチャーを支援したいと考えている。しかし同時にそれを行動に動かせない立場でジレンマを感じている。当初、著者が一ビジネスマンとして他社へ営業に行く際には、その基本的な方法やビジネスマナーすらも手探り状態で、知らず知らずのうちに失礼な態度を取ってしまったこともあった。しかし、そうした態度にもかかわらず、気分を損ねるどころか親身になって相談にのってもらえたり、厚い激励を受けたりすることもしばしばで、「個人的に可能な支援であれば何でもしたい」と言われたことも実際にあった。そうした心境の奥底には、まだ成長段階の企業や学生を支援することを時間や労力の投資とする考えだけではなく、自由な発想と行動力でビジネスを展開しようとする学生を純粋に支援したいという想いや、大学の先輩として半ば衝動的に支援したいと申し出てくる人もおり、そうした人との出会いがビジネスにおいて大きな後押しとなったことは言うまでもない。しかし、個人的感情では支援したいと思っても、それが有限会社ピー・アイ・ピーとの交渉や取引、つまり対企業となってしまうと感情では動けないもどかしさやしがらみに駆られている様子が強く窺い知れた。そこには上司を説得するための費用対効果の問題や、学生ベンチャー企業の継続性への不安、また実績の無い会社とは取引をしないという企業風土や慣習などがあり、実社会にはまだまだベンチャー企業を育てようとする土壌が整っていない現状が浮き彫りとなっていたように感じる。
次に、学生という立場それ自体への強い関心である。社会人は学生についてあまりにも情報が乏しいため、学生がどのような行動パターンをするのか、何に関心があるのか、何が流行りなのかを、学生から直接聞きたいと強く願っている。なぜなら学生を中心とする若者のトレンドは変化しやすく、かつ実社会と学生との間に大きな隔たりがあるため学生の事情が把握できず、マーケットの開拓が難しいためである。なかにはこの隔たりを埋めるべく、学生との接点を求めてpipプロジェクトとの関わりを求めてきた企業も多数あり、著者が少しでも学生の感覚や動向について話をすると大変喜ばれたのが印象的であった。こうした「学生の感覚」は、多くの企業にとってトレンドをつかみマーケティング戦略に活かせる有益な情報となるが、その「学生の感覚」を効果的に吸い出せている企業はごく少ないと感じる。「学生の感覚」を実社会に伝達する楔の役目を果たす人材や組織が強く求められており、その役割を学生ベンチャーが果たすことで学生ベンチャーの存在意義と社会的地位を確立できるのではないかと感じた。
2−3 学生の反応
著者が学生起業家選手権で優秀賞を受賞してから、周囲の学生や友人の自分に対する見方が一変した。友人をはじめとする周囲の評価が、大学生としての自分ではなく起業家としての自分に変化していったのである。ここまであくまで自然体で取り組んできた自分としては、根本的には何も変わっていない自分への評価が変わっていく様子に戸惑いすら感じた。
だが、そのこと自体はpipプロジェクトにはポジティブな要因となった。pipプロジェクトは学生に無料デザイン名刺pipを流通させようとするものであるから、学生が主体的にそれを使用しクチコミを広げなければならないが、自分達の周囲から自然とクチコミは広がり、結果的には当初の想定以上に学生ユーザーを囲い込むことに成功した[18]。これは、学生に割って入り学生を動かすのは学生が主体であることが極めて有利であることを意味している。
一方で、それまで知り得なかった学生コミュニティや意識の高い学生達との出会いや交流を持つことができ、新たな価値観に触れることが出来たのは大変刺激的であった。特に、起業を志す学生やそうした学生を支援する団体との関わりは、単に友人としての付き合いだけにとどまらず、新たな人的ネットワークとしてビジネスに新たスなアイデアをもたらしてくれるものであった。しかしながら、不思議とそうした起業への意識の高い学生や学生団体からは起業家が育っていない印象を受けた。実際にそうした団体の勉強会に、ゲストスピーカーとして招かれたりするなど、対話の機会が数回あったが、彼らは起業することを手段ではなく目的と位置付けているため、起業に対して大きく構えてしまっていた。そうしたスタンスで構える学生達に、pipプロジェクトメンバーが起業の経緯を説明すると、やはりその自然体な様子に驚かれたものである。
こうした学生や学生団体との出会いは、その後学生間にpipを認知させるためのクチコミを生み出す火種となった。
2−4 小括
現代では、学生起業家のイメージが先行し、本来の会社や起業した本人達の姿がかすんでしまっている傾向がある。特にメディアを通じたメッセージはその傾向が強く、pipプロジェクトでは、メディアに露出することで一時的な会員増加や話題性を得ることは出来たが、メディアを通じて実際の姿を伝えることができなかった。そのため、メディアの影響力を効果的に利用し継続させるまでには至らなかった。一方で、学生が運営する企業の最大の強みである「学生間のネットワークの構築」においては地道に学生団体や友人を通じて話をし、理解を深めてもらうことで少しずつ学生のクチコミを拡大することに成功した。
3‐1 産学の隔たり
以上述べてきたように、著者は学生起業家選手権を機に学生と社会人という二足の草鞋を穿いて約1年半を過ごした。この間、学生の自由な感性が実社会で理解されないもどかしさ、つまり産学の隔たりの大きさを常に感じてきたが、それは必ずしも学生の主張がビジネスにおいて間違った方向を向いているということではなく、一般社会人が予想もしないアイデアや発想を学生が提示していることに対して、トライアル的に採択させるだけの信用力やメリットが見受けられなかったということである。言い換えれば、学生と同じような感性や主張を信用力のあるビジネス界のキープレイヤーが出せるならば、学生マーケットを開拓することはそれほど難しいことではない。しかし、一度学生の立場を離れてしまった者にとってそれは極めて難しいのである。
3‐2 産学の隔たりの要因
3−2−1 学生の感覚に対する理解
学生のトレンドやニーズは変化しやすく、一度学生を離れて社会人になってしまうとその動向を掴み続けることは極めて難しい。そのため、学生にとってはごく自然な感覚であるにも拘らず、それを理解できる社会人は極めて少ない。産業界が学生のニーズやトレンドを掴み、マーケットを開拓するためには、常日頃から学生のダイレクトな声に耳を傾けることが必要である。
3−2−2 実社会の感覚に対する理解
実社会では、営業の仕方やビジネスの展開手法にトレンドがある。例えば広告業の場合は一昔前まで斬新でトライアルの価値があるものが採用される傾向にあったが、最近では不況と広告費削減の影響から、既存の媒体との比較によって数値的にその優位性を示さないと契約が取れない傾向にあるなど、その業界の事情や流行の手法が存在する。しかしながらそうした各業界のトレンドを学生が敏感に感じ取れるような仕組み、ならびに産学協同プログラムが不足している。
3−3 提言
著者は起業経験を通じて、産学の隔たりは想像以上に根深いものがあると感じた。しかし、産業界と学生の両方の立場を同時に体験した著者自信は、その隔たりを埋めることは決して難しいことではないと信じている。なぜなら学生をターゲットにしたビジネスを学生の視点で実現することで、ビジネスが成立することを体験的に理解しており、また企業の現場で活躍する多くの人と接し、その感覚も同時に感じ取ってきたからである。
近年、産学の隔たりを埋めるべく「学生の就業体験プログラム」や企業人を講師に招く「寄附講座」が浸透しつつある。しかしながら、現状の制度はで産学の隔たりを埋めるには不十分である。たとえば現状のインターンシップの多くは企業が学生にプログラムを提供する一方的なものに偏りがちであるし、企業人が講師として招かれるときにはその企業の重役や管理職などが多く、そうした講義ではマネジメントの視点を理解することはできても現場の最前線の様子が何一つ伝わってこないからである。
こうした一方的、断片的な産学の交流が成されるのではなく、学生の感覚とビジネスの現場のトレンドを共有できるよう、両者が現場レベルで歩み寄ることが極めて重要であり、それが実現できれば産学の隔たりを埋めることは十分に可能である。
著者の知る限りにおいても、実社会を知らない学生は多い。しかし、それを知りたいという意欲は持っている学生は決して少なくはなく、また学生は実社会に触れることを恐れたりはしているわけでもない。実社会を知るチャネルが不十分、及び機能していないため、大学を卒業して実社会に触れると想像していた以上に求められる社会的責任の大きさに尻込みしてしまうのである。
大学は学生と実社会との接点を創造し、また企業は社会的責任を学生に伝達するよう、それぞれの責務を負っているように感じてならない。
3−4 結びに代えて
著者がゼミナールのメンバーと共に立ち上げた有限会社ピー・アイ・ピーは、著者を含む創立メンバー3名が大学卒業を機に実務から退き、それぞれ新しいフィールドで実社会と関わっていく決断をした。会社は大学の後輩を中心とした現役大学生を役員に据える新体制で臨むが、創立メンバーの3名はそれぞれ出資者として経営に関わることになる。現役学生から現役学生への経営陣のバトンリレーは一般社会では極めて特異な例であり、そこには多くの不安や葛藤があったが、実際にはとりわけ大きな問題も無くスムーズな引継ぎができた。これも、「いち早く実社会を知りたい」というモチベーションの高い学生が経営に参加することを志願してくれたからに他ならない。自らの手で起業し、経営をしてきたことで人脈や経験を積み、そして次代への引継ぎを経験することで、正に「企業は人なり」であることを感じ取れたことは、著者にとって大きな財産となることは言うまでも無い。
本稿の結びに代え、有限会社ピー・アイ・ピーの在り方に共感し、自ら企業経営に関わることに強い関心を抱き、勇気を持って一企業の社会的責任を負うことを申し出てくれた9名の学生達(伊藤優士、遠藤敦子、北島すずみ、小泉典子、鈴木則昭、高山奨史、佛坂浩平、三山晋大朗、望月雅之)に敬意を表したい。
資料 1 設立開業準備費
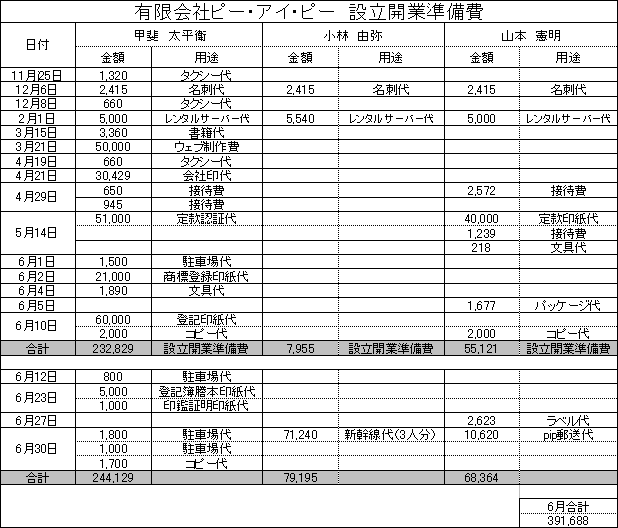
資料 2 商標登録願
 |
(21,000円)
【書類名】商標登録願
(【整理番号】)PIP-1
(【提出日】 平成 15年 6月 2日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
別紙の通り
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第35類】
【指定商品(指定役務)】
名刺,名刺ケース,フォルダ,ファイル,ストラップ
【商標登録出願人】
【住所又は居所】
東京都渋谷区道玄坂二丁目10番10号
【氏名又は名称】有限会社ピー・アイ・ピー
【代表者】甲斐太平衛
【電話番号】03-3705-****
【商標登録を受けようとする商標】
